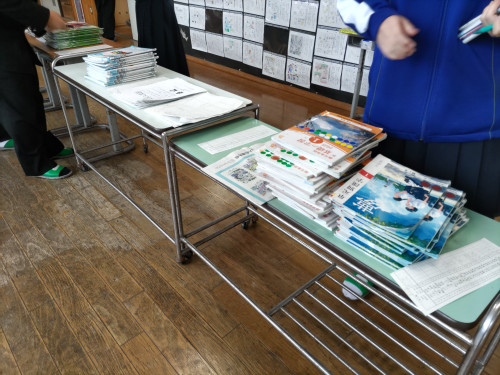本日1月8日(水)、3学期が始まりました。校内では感染症等は流行していませんでしたが、3年生の受験や感染防止等を考慮して、始業式はオンラインで行いました。 久しぶりのオンライン集会でしたが、何とかスムーズに行うことができました。
久しぶりのオンライン集会でしたが、何とかスムーズに行うことができました。
1年生代表生徒は、2学期の反省を踏まえ、計画性をもって家庭学習に取り組み、学習効率を上げ課題を克服すること。失敗を前向きに捉え、学級の支えとなれるように努力するとの内容でした。
2年生代表生徒は、これまでを振り返っての成長と課題を明らかにし、気の緩みや油断がないよう継続していくことの大切さや授業への取組を徹底していくこと。生活面では。持ち前の元気や明るさを生かしながら、授業によって態度が変わらないよう、学級・学年で話し合いながら改善していくという内容でした。
3年生代表生徒は、冬休みに生活のリズムを整え、入試前の自己管理・自己決定を行うことができたこと。一年間・中学校三年間・義務教育九か年の締めくくりとなる3学期にすること。学習は入試や3か月後を意識しながら課題へ取り組むこと、生活はあいさつや体力をしっかりとしていくこと。3学期を次のステージののゼロ学期と捉え、笑顔で卒業できるように努力するとの内容でした。
どの学年代表も立派な内容でした。これを聞いた他の生徒のみなさんも、自分の目標をぜひ有言実行してほしいと思います。
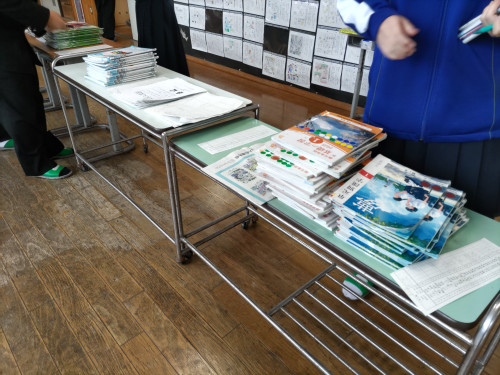 その後は学級活動で、恒例の「宿題提出」でした。相変わらず「先生、忘れてしまいました・・・。」と報告する生徒がいましたが、まぁこれも学期始めの風物詩ですね。早めの提出をお願いします。
その後は学級活動で、恒例の「宿題提出」でした。相変わらず「先生、忘れてしまいました・・・。」と報告する生徒がいましたが、まぁこれも学期始めの風物詩ですね。早めの提出をお願いします。
 2週間という短い期間でしたが、生徒のみなさんの表情からは充実した冬休みが送れていたようでした。3学期はまとめの学期です。次のステージに向けてともに頑張っていきましょう!
2週間という短い期間でしたが、生徒のみなさんの表情からは充実した冬休みが送れていたようでした。3学期はまとめの学期です。次のステージに向けてともに頑張っていきましょう!
 食事のマナーや栄養素等についての基本的な内容を押さえた後、1年生は体作りと食に関する内容、2年生は運動と食に関する内容、3年生は受験に向けて頭を働かせる食に関する内容について対話活動を取り入れながら行いました。
食事のマナーや栄養素等についての基本的な内容を押さえた後、1年生は体作りと食に関する内容、2年生は運動と食に関する内容、3年生は受験に向けて頭を働かせる食に関する内容について対話活動を取り入れながら行いました。 食事は生きていく上での基本となります。これから成長期真っ只中の生徒のみなさんにとっては、将来の自分の体を作る上での「食」について考えるよい機会となったと思います。三善先生、ありがとうございました。
食事は生きていく上での基本となります。これから成長期真っ只中の生徒のみなさんにとっては、将来の自分の体を作る上での「食」について考えるよい機会となったと思います。三善先生、ありがとうございました。